2016年第3回ワークショップ開催報告「ソーシャル・ステークホルダーマネジメント実践」
ソーシャルPM研究会 小谷野 正博
はじめに
2016年3月26日(土)に、ソーシャル・プロジェクトマネジメント実践ワークショップ 第3回 「ソーシャル・ステークホルダーマネジメント実践」が開催されました。私は運営メンバーの一員ですが、参加者の立場でワークショップの模様と感想を報告いたします。
セミナー概要
PMI日本支部のWEBにアクセスしようする方ならば、ステークホルダーマネジメントと聞けば、PMBOK®ガイド のステークホルダーマネジメントを思い浮かべるのではないでしょうか。
平たく言えば 「立場の違ういろいろな人間がいろいろなことを言うとプロジェクトは混乱するが、混乱の源となるステークホルダーを味方にする様マネジメントすれば、混乱は抑えられるはずだ」 ということ。
方法論としては 「早めにステークホルダーを特定し、その立ち位置を知り、影響力のある相手を味方にする作戦を立て、常日頃からそれを実践する活動」 となるでしょうか。
PMI日本支部WEBサイトの本ワークショップ募集案内にもあるように、「ソーシャル・プロジェクトは、多様なニーズがあって、焦点を絞れず議論が堂々巡りして前に進まない。」とあります。 さらに、マルチ・ステークホルダーという用語が出てきます。
まさにこの多様なニーズは多様なステークホルダーから来ているのでしょうから、ソーシャル・プロジェクトのステークホルダーマネジメントは企業内やビジネス・プロジェクトよりも複雑になるのではないか、ということは漠然と理解できます。残念ながら、PMBOK®ガイド をひもといても、そこからは有効な手だてが分かりません。
ソーシャルPM研究会の定義では、「ソーシャル・ステークホルダーマネジメント は、観察/体験から得られた人々の状況とその変化を事前期待として受けとめながら、関係者の期待やニーズを理解して解決への道筋を検 討していくマネジメント」 としています。
それではと、今回のワークショップでより多様で複雑なステークホルダーをマネジメントする手だてが学べるかもしれないとの期待がありました。
午前の講義で理解したこと
午前中は講義が中心で基礎理論を確認しました。
① ソーシャル・ステークホルダーマネジメントとは
② ソーシャル課題における「多様な主体による協働」の脆弱さの問題
③ マルチ・ステークホルダーへの注目
④ ステークホルダーマネジメントプロセス
⑤ 影響力発揮の原理・原則
 高橋理事によるオープニング | 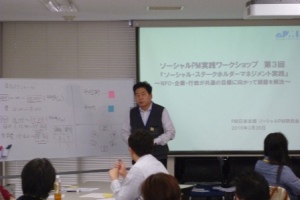 講義中の中谷講師 |
上記項目は中谷講師の「課題を解決する原理・原則があるとすれば、それは何であるのか。」との問いかけにより進められました。
この何であるのかを、書籍『影響力の法則』、『なぜ人と組織は変われないのか』、『持続可能な発展とマルチ・ステークホルダー』、『サーバント・リーダーシップ実践講座』等から解決ツールとして示し、次々と紹介されました。
印象に残ったツールは下記の4つです。
《マルチ・ステークホルダーマネジメントの5つの重要成功要因》・・・ステークホルダー間の関係を進化させるには、対等性、目的・ビジョンの共有、相互信頼、相互変容、価値創造について考える。
《カレンシーの交換》・・・反対aの立場をとる人に、その人が価値があると感じているもの(カレンシー)bを提供することで、反対を軽減させるaとbを交換するテクニック。
《サーバント・リーダーシップ》・・・リーダはチームメンバに奉仕するとともに、ミッション、ビジョン、バリューを示さなくてはならない。
《免疫マップ》・・・人には変化に対する不安がある。その根底には変化を阻む免疫があるからだ。それをマップにすることで、免疫を排除する対策を立てることができる。
これ以外のツールも含めて、私にとっておおかたが不案内でした。ステークホルダーマネジメントの重要性は理解しているものの、全く踏み込んで実践していない領域だと痛感しました。
そのため、これらツールがソーシャル課題のステークホルダー課題解決にフィットしているのか、その時の私にはまだ十分には分かりませんでしたが、実践していない現在、仮説・検証を繰り返す必要があり、これらのツールは仮説を作るツールだと思えばよいと理解しました。
午後のワークショップで理解したこと
午後は、午前の講義の理解を深めるワークショップでした。
ワークショップでは 参加者25名が 5人ずつ 5チームにわかれました。どの1チームでも過去2回のワークショップに参加された方が2~3人は居られたので、それぞれのチームはスムーズにディスカッションや作業が進みました。
今回は「市役所が福祉と連動した食品トレーリサイクル事業を推進する」という内容でした。
ステークホルダーとしては、
① 市役所(市長、課長、係長、係員)・・・事業を推進する
② 福祉団体1&2・・・障害者にトレーの回収や洗浄する仕事を提供する
③ トレー商品提供者・・・きれいなトレーを商品として完成し販売する
④ スーパマーケット・・・トレーを購入し使用する
これらステークホルダー間にはそれぞれ思惑があり、代表する人たちの人間性もそれぞれです。また、市役所の担当部署内でも同様です。私たちが日ごろ悩まされている状況が映し出されます。あらためて、人間関係処理がストレスの源だと思い知らされます。でも避けて通れません。
ワークは以下のフローに従って進めました。
① ステークホルダーを特定する
② ステークホルダーについて賛否、関心度、影響度を評価する
③ ステークホルダーを4象限に分類する ④ 変われないキーマンの免疫マップを作成する
⑤ 変われないキーマンの目標への道のりを作成する
⑥ プロジェクト遂行上の重要なステークホルダーを特定する
⑦ 重要なステークホルダーに係るリスクと戦略を立てる
⑧ ステークホルダーにエンゲージメントする
中谷講師のリードにより、午前で得た知識とツールをこのようにワークを通じて練習すると、しっかりと腑に落ちてきます。また、チームメンバはそれぞれ異なる着地点を発案しますが、議論で集約された着地点は、また別のチームの着地点と違ったものになります。 ステークホルダーマネジメントは人間関係を扱うので、現実には最適解が有るような無いようなものです。
通常、私たちはステークホルダーマネジメントの重要性を理解しながら、実際はQCDSの管理と問題解決に忙殺されています。中谷講師いわく「80%の人が理解・同意するが、実践する人は20%」とのこと。実践するには、今回ワークショップで学んだ知識とツールで仮説・検証をするのだと思えば踏み出せると感じました。
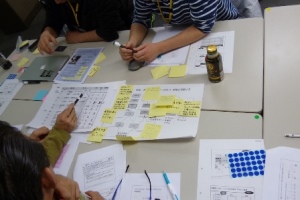 チームでの検討 |  ステークホルダーの免疫マップ |
参加者からのコメント
ワークショップを終えた参加者からは、
- カレンシーでの「素早い対応」が相手への報酬になるということが印象に残った。仕事に活かしたい。
- 紹介していただいたツールは社会活動ばかりでなく、担当しているITプロジェクトにも役立つので、出典の書物を読んで仕事に生かしたい。
- ソーシャル・ステークホルダーマネジメントが会社の利害関係の強いプロジェクトとは違う難しさがあることが分かりました。
- セクターを超えたステークホルダーには権限以外の影響力をもって関わる必要があることを理解しました。
- なぜ人は動かないのか、また権限を使わずに人を動かすにはどうすればいいのかを学べました。
- 講義で習ったすぐ後に、頭と手を動かしてグループワークすることで知識の定着や本質への洞察が得られ、理解をますことができた。
といった感想をいただきました。 これらの声は今後のワークショップやソーシャルPM研究会の活動に活かしたいと思います。
以上