2016年第4回ワークショップ開催報告「ソーシャル・ポートフォリオマネジメント実践」
2016年 6月21日
ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会 石塚 幸夫
はじめに
2016年5月21日(土) にPMI日本支部 セミナールームで開催された、『ソーシャル・ポートフォリオマネジメント実践』を受講しましたので、ご報告します。
ワークショップのテーマ
第1回「ソーシャル・デザイン思考」、 第2回「ソーシャル・ベネフィットマネジメント」、 第3回「ソーシャル・ステークホルダーマネジメント」に続き、ソーシャルPM実践ワークショップの6回シリーズの第4回は「ソーシャル・ポートフォリオマネジメント実践」です。
ソーシャルPM研究会では、ソーシャル・ポートフォリオマネジメントを『ソーシャル課題に対する複数の解決策を評価、選定、優先順位付けして、限りある資源を有効に配分することによって、創出する「共有価値を最適化」するマネジメント』と定義しています。
午前の講義で学んだこと
ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会の代表である高橋講師から、社会活動における、ポートフォリオマネジメントの特徴について説明を受けた後、東京圏一極集中化に伴い、全国1,800余の地方自治体の約半数が消滅する可能性があるというショッキングな予測があり、内閣官房主体による、「まち・ひと・しごと創生」施策を受けて、各地域が長期ビジョン、総合戦略を策定中という、まさに直面している、社会問題をご紹介いただきました。
ソーシャル・ポートフォリオマネジメントについての3つの論点を
- 目的:「正しいことを正しく行う」
- 意思決定:ソーシャル・インパクトとソーシャル・キャピタル
- プロセス:行動の最適化を図るソーシャル・ポートフォリオ
と定義するとともに、以下のとおり、6つの活用シーンを想定し、ポートフォリオマネジメントの適用手順、手法について説明していただきました。
- ソーシャル課題の定義、選択と集中、評価方法(活用シーン1~3)
(手順1)ソーシャル・デザイン思考により、課題再定義から~複数解決策を洗い出す - ポートフォリオ定義:(活用シーン4)選定・優先順位付け
(手順2)プロジェクトの特定 (ツール:ベネフィットマップ)
(手順3)社会価値の評価 (ツール:ソーシャル・インパクトリスト、ソーシャルキャピタルリスト)) *ソーシャル・インパクト(社会的インパクト):活動や投資によって生み出される社会的・環境的変化 *ソーシャルキャピタル(社会関係資本):社会的ネットワークとそこから生まれる信頼、規範といった、共通の目的に向けて効果的に協働活動へと導く社会組織の特徴
(手順4)優先順位づけ (ツール:スコアリング・モデル) - ポートフォリオ最適化(活用シーン5)、資源配分
(手順5)バランス調整 (バブルチャート) - 環境が大きく変わった時) ポートフォリオ再調整: (活用シーン6)
(手順6)環境変化対応 (目標再設定)
(手順7)戦略変更 (経済価値の評価)
午後のワークショップで学んだこと
ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会のWG4(実践WG)のリーダーである、藤井講師のリードで、1チームあたり5人×5チームに分かれて、課題に取り組みました。
主要な産業が林業、酪農、高原リゾート地としての観光資源に富み、バイオマス発電にもチャレンジしている地方自治体をケースとして取り上げました。この自治体では、進む過疎化への戦略として、①雇用創出、②交流・定住、③子育て・教育、④都市づくり の具体的な施策を推進しており、事業計画や「市長の所信表明」を基に、受講者は自治体の総合戦略の投資委員会に参加する組織のメンバーとして、最終的な意思決定を行う市長に提言するミッションを持つ立場として、課題に取り組みました。
リアリティに富んだケースについて、午前中の講義で学んだ一連の手順、手法を適用し、チームメンバーとディスカッションしつつ、最終的には市長への提言を作成することを経験しました。
 |  |
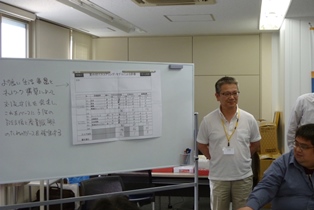 | |
中谷講師による総括
第1回~第3回のワークショップの講師を担当し、今回のワークショップの監修を担当された中谷講師が、総括を実施するともに、受講者のコメントに対し、実践的にアドバイスされ、複数回参加の方はさらに理解度を高めることができ、初回参加の方も重要なポイントについて確認できました。
 |
参加者からのコメント
以下、一例をご紹介いたします。
「ソーシャルキャピタル、ソーシャルインパクトを軸にデザインしていくことが有効なプロセス、手法であることを認識できたので、自分が行っている社会活動に適用してみたい。」
「正しいことを正しく行うという定義が心に響いた。 講義、ワークショップを行うことで、進め方、優先順位の付け方など、どのように取り組めばよいか実感できるようになった。」
「ソーシャルキャピタル、ソーシャルインパクトの数字、エビデンスを収集する指示があるが、その意図が自分のグループ内で十分に共有されていないことがあったが、今回学んだことを説明すればよいと思った。」 (国際交流団体に勤務されている参加者)
「前回学んだ、多種多様なステークホルダーのソリューション、意見をどのようにマネジメントすれば良いかイメージしきれていなかったが、腑に落ちるようになった。」
「PM手法である、デルファイ法が意思決定する際に効果的な手法であることを再認識した。」
「チームのメンバーとのディスカッション、他チームの発表を通じて、さまざまな観点での優先順位付けがあることを認識しつつ、ロジカルな合意形成の仕方を体験できた。」
おわりに
ソーシャルPM実践ワークショップの6回シリーズの5回目『ソーシャル・ビジネスモデルデザイン実践』(8/27開催予定)、6回目『ソーシャル・アジャイルマネジメント実践』(9/24開催予定)への興味がさらに深いものになりました。
今回を含めた4回のワークショップで学んだことをソーシャルの活動に適用し、実証してみるとともに、さらに今後のワークショップやソーシャルPM研究会の活動に活かしていきたいと思います。
以上
