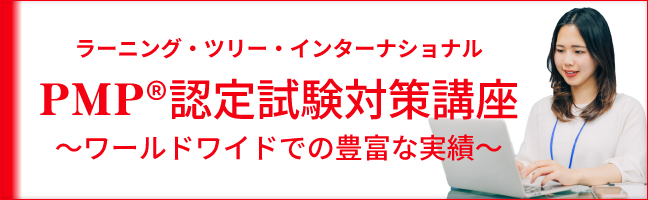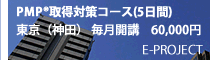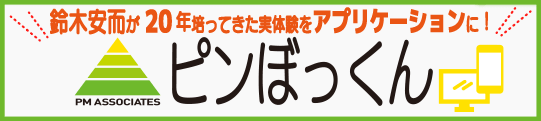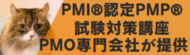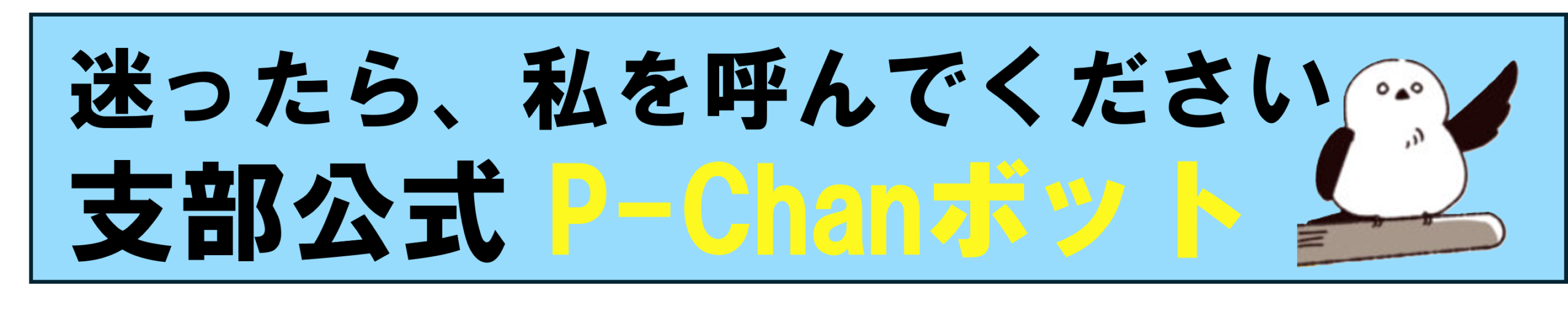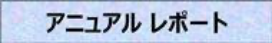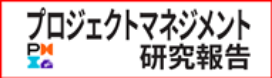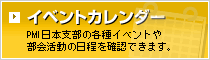部会紹介
戦略委員会
| 組織拡大委員会 | *メンバー募集中* 個人会員および法人スポンサーの増加につながる施策を検討・実施しています。 お知らせ PM Award 未来創造WG PMoA |
|---|---|
| 標準推進委員会 | PMIの標準書、実務ガイド等を調査、選択、邦訳し、日本のPMコミュニティへ提供することをミッションとして活動しています。 |
| 教育国際化委員会 | *メンバー募集中* 国内外の国内におけるプロジェクトマネジメント(PM)教育の実践活動の調査研究を通じて、国内におけるPM教育の啓発・普及を戦略的に推進するための委員会です。 |
| PMコミュニティ 活性化委員会 | *メンバー募集中*部会・研究会や PMI日本支部会員間のコミュニティが活性化するように、適切な情報を配布し、アクティブメンバーを質・量ともに増強する目的で新設された戦略委員会です。 |
| 地域サービス委員会 | *メンバー募集中* 首都圏以外の地域に対するサービス提供の企画・管理の役割を果たす。 |
| 国際連携委員会 | グローバルにおける日本支部のプレゼンス向上を目指し、海外への支部活動の紹介、表彰制度への応募、PMI本部やAPACそして近隣支部との関係強化を図っています。 |
| 会員サービス委員会 | ITシステム担当、情報発信担当、フォーラム・Festa・セミナー担当、事務局セミナー担当の4つの担当に分かれて会員へのサービス向上を目的に活動する委員会です。 |
委員会
| 戦略運営委員会 | 各種施策を立案し、活動を組織し、成果をモニターする。 |
|---|---|
| ミッション委員会 | PMI日本支部のあり方について理事会へ提言する。 |
研究会
| 統合プロジェクト・パフォーマンス・マネジメント(IPPM)研究会 | *メンバー募集中* 統合プロジェクト・パフォーマンス・マネジメント(IPPM)に関する情報収集・研究 |
|---|---|
| ビジネスアナリシス研究会 | *メンバー募集中* プロジェクトのためのビジネスアナリシス活動について理解を持つ人材を増やし、日本国内でのビジネスアナリシス活動の普及を目指していきます。 |
| アジャイル 研究会 | *メンバー募集中* アジャイル環境でのプロジェクトマネジメント手法の適用と有用性などについて、議論や実地検証を行いながら情報発信に取り組んでいきます。 |
| ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会 | *メンバー募集中* 社会的課題の解決を目的とする活動(ソーシャル・プロジェクト)のマネジメントに適するプロジェクトマネジメント手法の開発・普及により社会に貢献する。 |
| PMツール研究会 | *メンバー募集中*PM品質を向上させるPMツールの実践的な利用法について、事例などを元に情報交換/討議する。 |
| PMタレントコンピテンシー研究会 | *メンバー募集中*タレントトライアングルを踏まえたPMのコンピテンシーを幅広く研究し、プロジェクトマネジメントタレントの育成の手法を研究する。 |
| PMO研究会 | *メンバー募集中* プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)について、事例収集に中心としたPMO研究活動を行う研究会 |
| PM翻訳出版研究会 | 当研究会は現在活動を休止しています。 |
| ポートフォリオ/プログラム研究会 | *メンバー募集中* ポートフォリオ/プログラムマネジメント標準を共通基盤とした、経営視点での研究・情報発信・適用支援 |
| リスク・マネジメント研究会 | *メンバー募集中* “リスク・マネジメント” に焦点を当てた文献研究/事例研究 |
| 組織的プロジェクトマネジメント研究会 | *メンバー募集中* 組織的プロジェクトマネジメント成熟度に関するPMI標準であるOPM3(Organizational Project Management Maturity Model)の研究、普及 |
| IT研究会 | 新規メンバーの募集は中止しています。 |
| PM教育研究会 | 「PM社会人教育」、「PM大学院教育」、「PM大学教育」、「PMジュニア教育」の領域で実践的教育プログラムを提供する活動を行っています。 |
| IRC (International Relation Community Study Group) | *メンバー募集中* 海外のPM組織との連絡およびPM知識の紹介など |
| ステークホルダー・エンゲージメント研究会 | *メンバー募集中* ステークホルダー・パフォーマンス領域を中心にエンゲージメント手法を文献や実例など広く研究し会員と共有する。 |
| プロジェクトマネジメント研究会 | *メンバー募集中* PMBOK(r)ガイドの研究や情報発信、プロジェクトマネジメント全般についての研究、幅広い意見交換の場(PM-ZEN)開催 |
| SDGsスタートアップ研究会 | *メンバー募集中* 世の中の各種SDGs活動立ち上げと推進が効果的に進むよう、SDGsスタートアップ方法論の開発と普及促進、SDGsプロジェクトへのアドバイス、SDGs/ESG/CSV等の調査研究、情報発信などを行っています。内閣府「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」 内に「SDGsスタートアップ研究分科会」を設立し運営しています。 |
| はじめてのプロジェクトマネジメント研究会 | *メンバー募集中* 本研究会では、初心者や若手の方々が気軽に参加できる環境を提供し、プロジェクトマネジメントの知識やスキルを楽しく学びながらキャリアアップを目指します。 |
| ミドルキャリア研究会 | *メンバー募集中* 本研究会では、キャリアを軸に同世代のPMがつながり、対話と共創を通じて次のキャリアステージを考える場です。経験やモヤモヤを持ち寄り、安心して語り合えるサードプレイスを目指します。 |
関西ブランチ
| 関西ブランチ | PMI 日本支部 関西ブランチの部会活動、イベント・セミナーなどに関する情報への… |
|---|---|
| 関西ブランチ代表からのご挨拶 | 関西地区代表からご挨拶申し上げます |
| PM創生研究会 | *メンバー募集中* 関西にて日本のプロジェクト風土に合ったマネジメント研究の活動 |
| 定量的PM事例研究会 | *メンバー募集中* 関西にて定量的プロジェクトマネジメントに関する事例研究の活動 |
| IT上流工程研究会 | *メンバー募集中* 関西にてITプロジェクトの上流工程課題研究の活動 |
| 医療プロジェクトマネジメント研究会 | *メンバー募集中* 関西にて医療業界へのプロジェクトマネジメントの知識導入・実践研究の活動 |
| 関西ブランチ運営委員会 | *メンバー募集中* 関西の特徴を活かしたPMコミュニティを構築することにより、関西の活性化とプロジェクトマネジメントの価値向上に貢献する。 |
| プロジェクトマネジメント実践研究会(PM実践研究会@KANSAI) | *メンバー募集中*関西にてプロジェクトマネジメントの実践研究の活動 |
中部ブランチ
| 中部ブランチ | 中部地域におけるPMI日本支部の活動をさらに強化するため、中部ブランチを発足致しました。 |
|---|---|
| 中部ブランチ代表からのご挨拶 | 中部ブランチ代表よりご挨拶申し上げます。 |
| 中部ブランチ運営委員会 | *メンバー募集中* |
| PMサロン/セミナー | *メンバー募集中* |
| 地域ソーシャルマネジメント研究会 | *メンバー募集中* |
アカデミック
| アカデミック | 教育分野におけるプロジェクトマネジメント(PM)教育の普及を目的とした活動を展開しています。 |
|---|
プログラム
| PMBOK®セミナー・プログラム | *メンバー募集中* |
|---|---|
| セミナー・プログラム | *メンバー募集中* 各種セミナーの企画・実施 |
コミュニティ
| DAコミュニティ | *メンバー募集を再開しました。(2025年5月21日)* DAコミュニティはディシプリンド・アジャイルの適用方法、活用方法をみなさんと学習・研究することを目的に設立されたコミュニティグループです。 |
|---|---|
| 女性コミュニティ | 女性リーダーや女性PMが作るネットワーク。PMI日本支部の会員でなくても、コミュニティメンバーとして参加できます。 |
| AI@Work | *メンバー募集中* AI@WorkはAIの適用・活用をプロジェクトマネジメントの視点で捉え、あるべき姿や進め方を探求する事を目的とした活動です。 |
| 未来創造コミュニティ | *メンバー募集中* 「未来創造コミュニティ」は、「Com-Learn」という共通理念のもと、「共に学ぶ」を創出する場を目指し、実践経験の共有やCAPM®など共通の目標とする勉強会、ネットワーキングなどを通じて、相互研鑽を目的としたコミュニティです。実務力の向上につながる場として、ぜひ参加をお待ちしています。 |
| 建設コミュニティ | *メンバー募集中* 「建設コミュニティ」は、建設関連分野に携わる方が集い、PMBOK®ガイド*をベースにしつつ、この業界、分野におけるプロジェクトマネジメントを学び、交流し、研究・ワークショップ等により知見を深めてゆくことを目的としたコミュニティです。PMI日本支部内外のプロジェクトマネジャーの方々にとって、学び、交流、情報交換の場になることを目指しています。 |
| 行政コミュニティ | *メンバー募集中* 「行政コミュニティ」は、行政や行政を通した地域の取組みの価値創出に貢献するために設立したコミュニティです。どなたでも参加できる組織ですので、関心を持たれた方のご参加お待ちしております! |
| 地域コミュニティ | *メンバー募集中* 「地域コミュニティ」は、首都圏以外の全国諸地域の方を対象とした、地域内、地域間でPM活動、交流、研究を促進することを目的としたコミュニティです。現在、北海道、東海・富士、中国@広島、九州の4つのWGがあります。 全国で仲間を増やしましょう。 北海道WG 東海・富士WG 中国@広島WG 九州WG |
| シニアコミュニティ | *メンバー募集中* 「シニアコミュニティ」は、シニアが主体的に生きていける「社会」「コミュニティ」を醸成していくために、自らライフデザインができる「場」を提供することを目的としています。PMI日本支部のコミュニティとして活動しており、PMI日本支部会員以外の方もご参加いただけます。 |